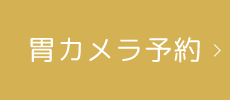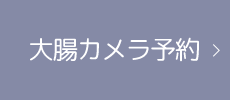ご来院の際は事前にWEBにて予約・問診の入力にご協力をお願いします。
ご不明な点はお電話にてお問い合わせください。
胆嚢性筋腫症とは
胆嚢の壁が、全体あるいは部分的に厚くなる良性疾患です。胆嚢壁が3 mm以上あると胆嚢性筋腫症と呼ばれます。
胆のう内に結石(胆石)ができたり、胆のう壁の内部に袋状の空洞(RAS)が増殖したりする特徴があります。通常、発症しても自覚症状がなく、健康診断や人間ドックなどの超音波検査(エコー検査)で偶然発見されることの多い病気です。好発年齢は40代~60代です。
無症状でかつ、がん化の疑いがない場合には治療不要であり、超音波検査(エコー検査)などで定期的な経過観察を行っていきます。一方で、胆のう炎を起こすと、腹痛・背部痛・吐き気・腹部膨満感などの症状が現れます。症状があり、胆石・胆のう炎との合併、胆のうがんとの鑑別が難しい場合などでは、外科的手術による胆のうの摘出術が必要となります。近年は体への負担が少ない腹腔鏡手術が主流となっており、手術することにより良好な経過が得られます。
胆のうとは
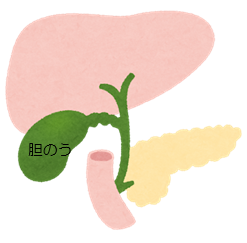
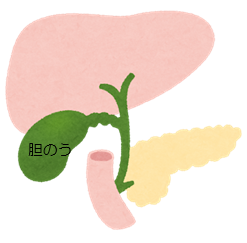 胆のうとは、袋状の形をした臓器で、肝臓と十二指腸を繋ぐ管(胆管)の途中にあります。
胆のうとは、袋状の形をした臓器で、肝臓と十二指腸を繋ぐ管(胆管)の途中にあります。
肝臓で作られた胆汁(たんじゅう)を一時的に50~60ml程度蓄え、濃縮する働きをしています。食べ物の消化・吸収に関与する胆汁は肝臓で作られ、胆管を通り、十二指腸に流れていきます。
胆嚢性筋腫症の原因
胆のう腺筋腫症の原因は、今のところはっきり分かっていません。
いくつかの仮説がとなえられています。
- 胆石症などと同じように、年齢や性別によるホルモンバランスの変化が影響しているとする説です。ちなみ好発年齢は40~60歳代で、男性は女性の2倍程度多いとも報告されています。
- 慢性的な炎症が原因とする説。ただ慢性炎症は原因なのか、胆のう腺筋腫症が発生した後に結果として慢性炎症が起こっているだけなのか、はっきりしません。
- 胆のう内圧上昇に伴って胆のう壁のくぼみであるRASが発生し、その影響で胆のう壁が肥厚するというストーリーです。
いずれも証拠に欠けており、結局は原因を特定するに至っておりません。
胆嚢性筋腫症の分類
胆のう腺筋腫症では、胆のうの全体または部分的に分厚くなりますが、病変が現れている部位や広がり方によって、次の3つに分類されます。
限局型(底部型)
胆のうの底(胆管接続部とは反対側)を中心として、限られた範囲で胆のう壁が厚くなっているタイプ
分節型(輪状型)
胆のうに「くびれ」ができて、2つに分節したタイプ
びまん型(広範型)
胆のう壁の広範囲で厚くなるタイプ
なお、発症の頻度は、限局型>分節型>びまん型の順に多いとされます。
胆嚢性筋腫症の症状
 主に無症状です。
主に無症状です。
胆石ができたり、胆のう炎を伴ったりすると、周期的にみぞおちを中心とした激しい痛み・右肩や背中の痛み・圧迫感・腹部膨満感などの症状が現れることがあります。また、胆のうがんの合併も少数ですが報告されています。
胆嚢性筋腫症の検査
超音波検査・腹部CT検査
・MRI検査・ERCP(内視鏡的逆行性胆管膵管造影検査)
超音波検査でわかります。しかし中には悪性のものもあり、鑑別が難しいので、 MRIで精査をします。
腹部CTは、超音波検査において、病変部が分かりづらい、悪性腫瘍(胆のうがん)が疑われるなどの場合に行うことがあります。
内視鏡的逆行性胆管膵管造影検査(ERCP)は、直接的に胆のう内部の病状が現れている部分を映し出すだけでなく、胆のう・胆管内の胆汁を採取して細胞診を行なうことにより、患部の質的診断(がん化しているのかどうかの診断)が可能です。
胆嚢性筋腫症の治療
症状がなければ無治療ですが、半年から1年ごろに超音波検査で経過観察を行いましょう。症状がある場合や胆嚢癌との鑑別が難しい場合は、腹腔鏡下胆嚢摘出術を行います。
腹腔鏡下胆のう摘出術
近年は、小さい穴から治療ができ、開腹手術と比べて体への負担が少ない「腹腔鏡下」での手術が多くなっています。腹腔鏡下胆のう摘出手術は、日帰りもしくは1泊程度の入院で実施し、手術時間は1時間~2時間程度です。ただし、胆のうがんを合併するなど、一部のケースでは「開腹手術」となることがあります。