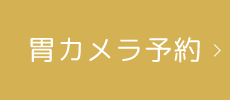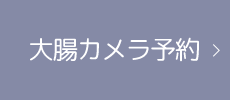ご来院の際は事前にWEBにて予約・問診の入力にご協力をお願いします。
ご不明な点はお電話にてお問い合わせください。
食道静脈瘤とは
 食道粘膜下を通る静脈が太く曲がりくねって、凸凹(でこぼこ)と瘤(こぶ)のようになった状態のことです。
食道粘膜下を通る静脈が太く曲がりくねって、凸凹(でこぼこ)と瘤(こぶ)のようになった状態のことです。
肝硬変などが原因で門脈圧亢進をきたすようになり、食道の静脈が拡張・怒張した状態になります。通常は食道に静脈瘤ができても自覚症状はありません。食道の下部に好発し、破裂すると大量の出血をきたすため、予防的治療が重要です。
破裂しやすく、未治療での出血死亡率は10%前後です。
肝硬変の約7割に合併するとされ、静脈瘤が発達すると破裂して消化管内に大出血を起こす恐れがあります。昔と比べて医療管理が進歩した現在でも、静脈瘤が破裂すると約20%の方が命を落としてしまうため、破裂の危険性がある場合には予防的に治療を受ける必要があります。
食道静脈瘤の原因
 食道静脈瘤の主な原因は、肝硬変などの肝臓異常による門脈圧の上昇です(門脈圧亢進)。肝硬変以外にも門脈圧亢進を起こす疾患として、特発性門脈圧亢進症、バッド・キアリ症候群、慢性すい炎、肝がん、膵がん(すいがん)などがあります。
食道静脈瘤の主な原因は、肝硬変などの肝臓異常による門脈圧の上昇です(門脈圧亢進)。肝硬変以外にも門脈圧亢進を起こす疾患として、特発性門脈圧亢進症、バッド・キアリ症候群、慢性すい炎、肝がん、膵がん(すいがん)などがあります。
食道静脈瘤の仕組み
肝臓の異常により、肝臓へ血液が流入しにくくなる か 門脈の圧力が高くなり、血液が滞る
血液が別ルートに流れるようになる(食道・胃の表面の血管を通る)
細かった血管も流れる血液が多くなるとだんだんと太く脆くなる
血管がデコボコして、こぶのようになる
食道静脈瘤の症状
無症状です。通常、静脈瘤の発症原因となっている肝硬変などの基礎疾患による症状のみとなります。
肝硬変の症状
 疲れやすい・全身倦怠感、食欲不振、進行すると黄疸(おうだん:皮膚・白目が黄色くなる)、腹水・むくみ(お腹・手足に水が溜まる)など。
疲れやすい・全身倦怠感、食欲不振、進行すると黄疸(おうだん:皮膚・白目が黄色くなる)、腹水・むくみ(お腹・手足に水が溜まる)など。
一方で、食道静脈瘤ができると、硬いものを食べるなど少しの刺激で傷ついて出血しやすくなります。出血多量では死に至ることも少なくないため、静脈瘤の出血は肝硬変の三大死亡原因のひとつです。
破裂すると、次のような症状が現れます。
吐血(とけつ)
口から血を吐くこと。通常、食道・胃など上部消化管からの出血で、真っ赤で鮮やかな血液・少し赤黒い血液が黄色みを帯びた胃液と混じって吐き出されます。
下血(げけつ)
肛門から血が出ること。食道からの出血では腸を通るため、消化液によって血の色は赤色ではなく、黒い色調に変わります。血便ではなく、黒い便(タール便)となるので、注意が必要です。
貧血
静脈の破裂による過剰出血のため、急激な血圧低下・めまいが起こります(急性出血性貧血)。
食道静脈瘤の検査
 内視鏡検査(胃カメラ)・造影CTを行います。
内視鏡検査(胃カメラ)・造影CTを行います。
当院では、主に胃カメラを行います。内視鏡検査(胃カメラ検査)では、静脈瘤の形態や「破裂しそうかどうか」を確認して、破裂の危険性がある場合には予防的治療を行い、出血時には止血を含めた内視鏡的治療も可能です。
食道静脈瘤の治療
破裂を防ぐために予防治療が重要です。
静脈瘤の部位や形態、色調、発赤などの内視鏡所見や全身状態を参考に治療方針を決定します。
1.内視鏡的治療
- 内視鏡的硬化療法(EIS):第一選択です。
しかし、高度の肝機能障害、腎機能障害、出血傾向があれば行いません。 - 内視鏡的静脈瘤結紮術(EVL):これだけだと再発率が高く、EISを追加して行うことが多いです。
2.インターベンショナルラジオロジー(IVL)
血管像絵に、超音波検査、CTなどを利用して画像ガイド下で行う治療の総称。カテーテルを用いて血管内から病変部に到達して治療する血管系IVRと病変部に直接穿刺して治療する非血管系IVRに大別されます。
3.薬物療法
静脈瘤の治療までの破裂、出血予防、再発予防として、β遮断薬や亜硝酸薬などの投与をします。
4.手術療法
内視鏡的治療が発達し、適応頻度は減少しています。